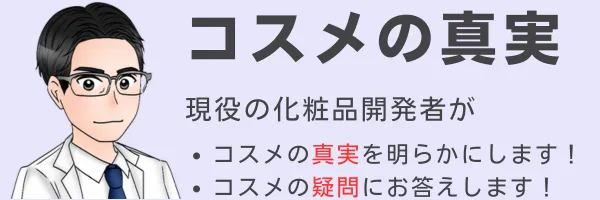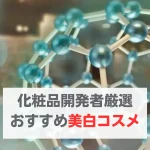この記事で分かること
- 化粧品の全成分表示の見方
化粧品のパッケージ裏に必ず記載されている「全成分表示」。
しかし、そこに書かれたカタカナや英語の成分名を見て、「何が入っているのか全くわからない…」と感じたことはありませんか?
実は、この全成分表示には化粧品選びを失敗しないための重要なヒントが隠されています。
本記事では、現役の化粧品開発者である筆者が、成分表示の読み解き方をわかりやすく解説。安全性や効果を見極めるためのポイント、避けたい成分、そして成分表示の裏側まで徹底的にお伝えします。
この記事を読めば、あなたも今日から化粧品の中身を見抜ける目を手に入れられるはずです!
この記事を書いている人

コスメデイン
- 大手化粧品メーカーで15年以上化粧品開発を担当
- 今も現役の化粧品開発者
- 美容雑誌の監修経験あり
- 現役の化粧品開発者が業界の最前線で得てきた知見を「コスメの真実」としてお届けします!
美容雑誌の監修に協力させて頂きました(一部抜粋)
全成分表示が始まった経緯

化粧品の全成分表示制度は、2001年から化粧品、2008年から医薬部外品にも義務化されました。
それ以前は、『表示指定成分』と呼ばれる一部の成分だけを表示すれば良かったのです。
旧厚生省が定めた、「人によってはアレルギーや肌トラブルを起こす可能性がある成分」のこと。
代表例:パラベンなど
2001年以降、この制度は廃止され、現在では「旧表示指定成分」と呼ばれることもあります。
代わりに、すべての成分を表示する方式に変更されました。
■ なぜ全成分表示に?
背景には、「国からメーカーへ責任を移す」という大きな方針転換があります。
以前は国(旧厚生省)が特定成分のみを指定・管理していましたが、制度改正後は「メーカーの責任で化粧品を製造・販売する」ことが求められるようになったのです。
| 制度 | 対象期間 | 表示内容 |
|---|---|---|
| 旧制度(表示指定成分) | 〜2000年 | 国が指定した成分のみ表示 |
| 新制度(全成分表示) | 2001年〜 | 配合されている全成分を表示 |
この変更により、ユーザーはパッケージを見れば「何が入っているのか」をすべて確認できるようになりました。
ただし、表示には厳格なルールがあり、これを理解しておくと化粧品選びに大いに役立ちます。
全成分表示の主なルール

化粧品の全成分表示には、いくつかの基本ルールがあります。
ここでは、理解しておくと化粧品選びに役立つ5つの重要ポイントをまとめました。
| ルール | 内容 |
|---|---|
| ① 配合量の多い順に表示 | 成分は基本的に、配合量の多い順に並びます |
| ② 1%未満の成分は順不同 | 1%未満の配合成分は、順番を入れ替えて表示してOK |
| ③ 医薬部外品は有効成分を先に記載 | 医薬部外品では、有効成分を最初に書き、その後「その他の成分」として残りを記載 |
| ④ キャリーオーバー成分は非表示可 | 製造過程でごく微量残るキャリーオーバー成分は、表示義務なし |
| ⑤ 香料はまとめて表示可能 | 複数の香料を使っていても、「香料」と一括表記が可能 |
もちろん、実際にはこれ以外にも細かな規定がありますが、まずはこの5つを押さえておけば十分です。
この後は、具体例を交えて、それぞれのルールをより詳しく解説していきます。
全成分表示から分かること

ここでは、実際の全成分表示を例に、成分の並び順やメーカーの意図を読み解いていきます。
■ 例①:化粧品(乳液)の全成分表示
水、プロパンジオール、グリセリン、スクワラン、イソステアリン酸ポリグリセリル-10、ジグリセリン、ホホバ種子油、月見草油、ゲットウ葉エキス、ユキノシタエキス、マグワ根皮エキス、ハトムギエキス、カンゾウ根エキス、ヒメフウロエキス、セラミド3、シロキクラゲ多糖体、ヒアルロン酸Na、ポリクオタニウム-51、トレハロース、ラフィノース、グリセリルグルコシド、ベタイン、グリチルリチン酸2K、水添レシチン、リゾレシチン、トコフェロール、スクレロチウムガム、キサンタンガム、シアノコバラミン、レウコノストック/ダイコン根発酵液、オクチルドデカノール、カプリル酸グリセリル、クエン酸、BG、フェノキシエタノール
- ルール①より、配合量の多い順に記載。
- ルール②より、ゲットウ葉エキス以下は1%未満成分で順不同。
植物エキスやヒアルロン酸などは、原価や安全性の面から1%以上配合することはほぼありません(原液化粧品は除く)。
メーカーは「イメージの良い成分」を上に持ってきて、多く入っているように見せることがあります。
逆に、防腐剤のようにイメージの良くない成分(例:パラベン、フェノキシエタノール)は、同じ1%未満でも一番下に記載し、目立たないようにします。
■ 例②:医薬部外品の全成分表示
有効成分 : グリチルリチン酸ジカリウム、プラセンタエキス(1)
その他の全成分 : 精製水、1.3-ブチレングリコール、濃グリセリン、プロピレングリコール、1.2-ペンタンジオール、水溶性コラーゲン液、シコンエキス、サクラ葉抽出液、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、アルニカエキス、シナノキエキス、スギナエキス、オトギリソウエキス、セージエキス、セイヨウノコギリソウエキス、ゼニアオイエキス、カモミラエキス(1)、トウキンセンカエキス、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カリボキシビニルポリマー、アクリル酸・メタクリル酸アルキル重合体、水酸化カリウム、パラオキシ安息香酸メチル、フェノキシエタノール、エタノール、青色1号、赤色106号、香料
- 医薬部外品は、まず、有効成分を記載し、その後に「その他の成分」を列挙。
- 水溶性コラーゲン液以下が1%未満成分。
- 「精製水」など、化粧品とは異なる成分名表記が使われる場合があります。
こちらも、上位にイメージの良い「エキス類」を配置し、下位に防腐剤(パラベン、フェノキシエタノール)を持ってくることで、見た目の印象を良くしています。
■ まとめ
化粧品や医薬部外品は、特に女性をターゲットにしているため、「イメージ戦略」がとても重要です。
全成分表示の並びにも、メーカーの工夫や意図が反映されているため、成分名だけでなく並び順や表示位置にも注目すると、より賢く商品を選べるようになります。
キャリーオーバー成分とは?

化粧品に使われる多くの植物エキスは、BGやエタノールなどの溶媒で抽出され、その抽出液の大部分は水で構成されています。
しかし、このままでは腐敗してしまうため、品質を保つために防腐剤(例:パラベン、フェノキシエタノール)が配合されます。
最終的な化粧品の効果や品質には直接影響せず、原料そのものの品質を維持するためだけに配合される成分のこと。
■ 具体例
- 植物エキスの抽出液に防腐剤が含まれている
- その防腐剤は完成品(化粧品)の性能には影響を与えない
- しかし原料の保存には欠かせない
この場合、防腐剤(パラベン、フェノキシエタノールなど)はキャリーオーバー成分として扱われます。
■ 表示ルールと注意点
- キャリーオーバー成分は全成分表示の義務がありません(任意で表示するメーカーもあり)
- 「パラベンフリー」と表示されていても、キャリーオーバー成分としてパラベンが含まれている可能性があります
- パラベンに強いアレルギーや過敏症がある方は、メーカーに確認することが重要です
注意 キャリーオーバー成分は完成品のパッケージからは分かりにくいので、敏感肌の方は特に注意!
全成分表示を意識した製剤検討

化粧品の開発担当者は、製品を処方設計する際に全成分表示を強く意識します。
■ なぜ全成分表示を意識するのか?
製剤担当者が最も避けたいのは、市場に出した化粧品が分離や変質などの安定性トラブルを起こすことです。
安定性に問題が発生すれば、市場回収や改良に多大なコストがかかり、ユーザーからの信頼も失われます。
安定性トラブルが起きた場合の流れ
- 市場から回収(状況によっては回収なしの場合も)
- 処方を改良
- 再度市場に投入
しかし、全成分表示が変わる改良をすると、箱や容器など全パッケージの作り直しが必要になり、莫大な費用が発生します。
■ 予防策としての配合順コントロール
製剤検討段階では、安定性に不安のある成分を把握しています。
もし想定外のトラブルが起きても、全成分表示に変更が出ないように配合順や量を調整しておくのがポイントです。
例:乳液の成分表示
以下のような表示があったとします。
- ホホバ種子油
- 月見草油
どちらも1%以上配合されています。
検討中に、月見草油が安定性に影響する可能性が分かった場合でも、使用感のため配合したいときは、ホホバ種子油の配合量を超えない範囲で加えます。
こうしておけば、トラブル発生時に月見草油を減量しても、1%未満成分の並び順に影響せず、全成分表示を変えずに改良が可能です。
ポイント 1%以上の成分の配合順が変わると表示変更が必要になるため、処方段階から順序と配合比率を戦略的に設計します
■ まとめ
化粧品メーカーや開発担当者は、製品イメージを良くするためだけでなく、万一の安定性トラブルにも備えて、全成分表示を戦略的に利用しています。
これは、コスト削減とブランド信頼維持のための重要な工夫です。
おわりに
いかがだったでしょうか?
ここまで、全成分表示から化粧品の真実を読み解く方法を、化粧品開発者の視点で解説しました。
■ 全成分表示が義務化された背景
2001年以降、化粧品、そして2008年以降は医薬部外品にも全成分表示が義務付けられました。
これにより、消費者は製品の配合成分をより詳しく知ることができ、安全性や品質を見極めるための大きな判断材料を得られるようになりました。
■ 全成分表示から読み取れるポイント
- 配合量の多い順に表示されるルール
- 1%未満の成分は順不同で表示できる仕組み
- キャリーオーバー成分は表示義務がない場合がある
- メーカーが「イメージ戦略」で成分順を工夫していること
これらのルールを理解すれば、
- 本当に有効成分が多く配合されているかの目安になる
- 防腐剤や添加物の位置から配合量を推測できる
- メーカーの意図や製品コンセプトをより深く理解できる
■ まとめ
全成分表示は、単なる「成分の羅列」ではなく、製品の背景や品質を読み解くための重要な情報源です。
この知識を活用すれば、見た目や宣伝文句に左右されず、自分の肌質や価値観に合った化粧品を選べるようになります。
あなたのコスメ選びが、より賢く・安全で・満足度の高いものになることを願っています。
※本記事の内容は個人の見解であって効果を保証するものではありません