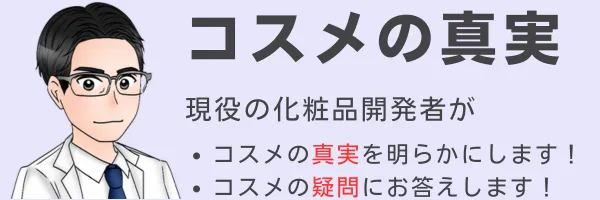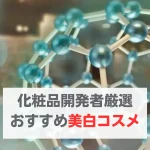この記事で分かること
- レチノールとビタミンCを一緒に使って大丈夫なのか
- レチノールの使用法と製品の選び方
大人気成分のレチノール。
美容効果が高いと期待される一方で、併用に注意が必要な成分もあるため、使いこなすためには知識が必要です。
特に、「ビタミンCと併用しても大丈夫?」という疑問をお持ちの方が多いようです。
私は現役の化粧品開発者です。
大手化粧品メーカーを含め、20年以上のキャリアがあり、有名美容雑誌の監修も多数手がけています。
本物のプロであり、化粧品開発のプロフェッショナルです。
この記事ではそんな私が、レチノールと他の美容成分との併用について、徹底解説します!
この記事を書いている人

コスメデイン
- 大手化粧品メーカーで15年以上化粧品開発を担当
- 今も現役の化粧品開発者
- 美容雑誌の監修経験あり
- 現役の化粧品開発者が業界の最前線で得てきた知見を「コスメの真実」としてお届けします!
美容雑誌の監修に協力させて頂きました(一部抜粋)
【結論】レチノールとビタミンCは併用不可?

以下が、化粧品及び医薬部外品の定義です。
薬機法第2条第3項(旧薬事法)に定められています。
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの
つまり、そもそも論として、化粧品及び医薬部外品は、作用が緩和で安全であることが大前提なのです。
ですから、レチノールとビタミンCの併用は、これらが化粧品及び、医薬部外品である以上、危険でも不可でもなく、併用は可能です。
ただし、レチノールとビタミンCは、併用不可ではないものの、併用に注意が必要な成分。
次項以降、詳しく解説します。
結論
- レチノールとビタミンCは併用可能
- ただし、併用には注意が必要
レチノールとビタミンC 併用時の注意点

どちらも人気の美容成分であるレチノールとビタミンC。
でも、この2つを一緒に使って大丈夫?と疑問に思ったことはありませんか?
■ レチノールとビタミンCが相性悪いと言われる理由
実はこの2つ、「pHの性質」がまったく異なるんです。
| 成分 | 最適なpH | 主な効果 |
|---|---|---|
| ビタミンC(アスコルビン酸) | 酸性 | 抗酸化作用・くすみ改善 |
| レチノール | 中性〜弱アルカリ性 | ターンオーバー促進・シワ改善 |
つまり、併用するとお互いの効果を打ち消す可能性があるのです。
■ 肌への刺激が増すリスクも…
ビタミンCとレチノールは、どちらも刺激の強い「活性成分」です。
この2つを同時に使うと、肌が過剰に反応してしまい、
- 赤み
- かゆみ
- ピリつき
といった副反応(A反応・過敏反応)が出る可能性があります。
注意
敏感肌・乾燥肌の方は同時使用を避けるのがベター
■ 「絶対併用NG」ではない。でも使い方に注意
レチノールとビタミンCは、併用そのものがNGというわけではありません。
仮に危険な組み合わせであれば、厚労省やメーカー(例:資生堂など)が規制や警告を出しているはずです。
しかし、以下のように、使用タイミングをずらすことで、安全かつ効果的に使うことが可能です。
おすすめの使い分け例:
- 🌞 朝:ビタミンC配合美容液(抗酸化・UVケア)
- 🌙 夜:レチノール配合クリーム(ターンオーバー促進)
※レチノールは光に不安定なため、夜の使用が推奨されます。
どうしても朝使いたい場合は、必ずUV対策(日焼け止め)を忘れずに!
ビタミンCとの併用まとめ
- レチノールは中性〜弱アルカリ性、ビタミンCは酸性 ⇒ 相性に注意
- どちらも刺激が強いため、肌に負担がかかる場合がある
- 併用するなら「朝ビタミンC、夜レチノール」がおすすめ
- 特に敏感肌の人は、慎重に使用量・頻度を調整すること
適切に使えば、レチノールもビタミンCも、肌にとって心強い味方です。
「同時に使うか」ではなく「どう使い分けるか」を意識して、美肌ケアに取り入れてください!
その他、レチノールと相性に注意すべき成分とは?

レチノールは非常に効果の高い成分ですが、一緒に使うことで刺激が増してしまう組み合わせも存在します。
ここでは、特に注意すべき成分と、逆に相性が良いとされる成分をご紹介します。
■ レチノール×サリチル酸・グリコール酸の併用はNG?
サリチル酸(BHA)やグリコール酸(AHA)は、角質を除去する働きがある成分です。
これらの酸とレチノールを同時に使うと、肌の剥離と再生が同時に起こるため、刺激や赤みなど肌への負担が大きくなる可能性があります。
注意
- レチノール×酸(サリチル酸・グリコール酸)=刺激リスク増大!
- 特に敏感肌や乾燥肌の方は、同時使用を避けた方がいい
| 成分名 | 分類 | 主な作用 |
|---|---|---|
| サリチル酸 | BHA(脂溶性) | 毛穴の詰まり改善、角質除去 |
| グリコール酸 | AHA(水溶性) | 角質層の剥離、肌の明るさ向上 |
■ レチノール×バクチオールは相性良し!
一方、バクチオールは植物由来の成分で、レチノールに似た作用を持ちながら、刺激が少ないのが特長です。
そのため、レチノールとバクチオールは併用可能なうえ、互いの効果を補完し合うことも期待できます。
| 成分 | 特徴 | 肌への刺激 |
|---|---|---|
| レチノール | ターンオーバー促進・シワ改善 | やや強め |
| バクチオール | 穏やかなレチノール様作用 | かなり低刺激 |
併用のコツ
- 最初は単体で使用し、肌に合うか確認
- 刺激がないことを確認してから、夜に重ねて使用
- 日焼け止めは必須(特にレチノール使用時)
バクチオールは、レチノールの効果をマイルドにしたい方や、敏感肌の人の導入ステップとしてもおすすめです。
■ まとめ:併用OK?NG?レチノールの組み合わせ早見表
| 組み合わせ | 併用の可否 | 注意点 |
|---|---|---|
| レチノール×サリチル酸 | △ | 肌への刺激増。交互使用推奨 |
| レチノール×グリコール酸 | △ | 併用は負担大。日を分けて使用 |
| レチノール×バクチオール | ◎ | 相性良好。肌の様子を見ながら使用 |
併用する際は、必ず肌の反応を確認しながら、使用量や頻度を調整するようにしましょう。
一つ一つの成分の特性を理解し、賢く取り入れることで、あなたのスキンケア効果を最大化できます。
【保存版】レチノールを安全&効果的に使うための完全ガイド

レチノールは肌のハリ・シワ・くすみなどにアプローチできる人気の美容成分ですが、刺激が強いため、正しい使い方をしないとトラブルの原因になることも。
ここでは、初心者の方でも安心して使えるように、安全な使い方・効果的な使い方・製品選びのポイントをまとめてご紹介します。
■ レチノール使用の基本5ポイント
✅ 使い始めの注意点
- 低濃度からスタート : 初心者は0.01%〜0.1%程度が目安
- 使用頻度を調整 : 最初は週1回、慣れてきたら週2〜3回へ
- 使用量は少なめに : 米粒大から始めて様子を見る
- しっかり保湿 : レチノール後は必ず保湿クリームでバリアサポート
- 紫外線対策を徹底 : 日中はSPF30以上の日焼け止めを使用
■ 効果を高めるスキンケアの順番&タイミング
レチノールの効果を最大限引き出すには、使用する順序とタイミングが重要です。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 洗顔 | 皮脂・汚れ・角質をオフ |
| ② 化粧水 | 肌に水分を補給 |
| ③ 乳液・保湿剤 | 肌を整え、レチノールの刺激を軽減 |
| ④ レチノール | 夜に使用(刺激が強いため) |
| ⑤ 朝のケア | 必ずUVケアを徹底 |
ワンポイントアドバイス
- 敏感肌の方は、レチノールを使う前後で保湿クリームをはさむ「サンドイッチ塗り」もおすすめ!
■ 初心者向け:レチノール製品の選び方ガイド
初めてレチノールを使うなら、以下の5つのポイントをチェックしましょう。
| 項目 | チェックポイント |
|---|---|
| ① 濃度 | 0.01〜0.1%の低濃度製品からスタート |
| ② ブランド | 信頼できるメーカーや皮膚科医監修の製品が安心 |
| ③ 成分 | ヒアルロン酸・ナイアシンアミドなど保湿成分配合が◎ |
| ④ 使用方法 | 具体的な使用手順が明記されている製品を |
| ⑤ 口コミ | 実際に使った人のレビューやSNSの反応をチェック |
■ まとめ:レチノールは「少量・低頻度・高保湿」が基本!
- 最初は週1回・米粒大でOK!
- 保湿と日焼け止めをしっかり併用
- 肌に慣れてきたら、頻度や濃度を少しずつアップ
- 製品選びは「低濃度」「信頼ブランド」「保湿成分配合」がポイント
正しい使い方を知っていれば、レチノールは美肌への強力な味方になります。
焦らず、肌と相談しながら、じっくりと“育てるケア”を楽しみましょう!
おわりに
いかがでしょうか?
レチノールは非常に優秀な成分ですが、使用方法や製品選びには注意が必要です。
決して併用不可ではないですが、ビタミンCやグリコール酸、サリチル酸などと併用する際は、刺激が強くなる可能性があるため、例えば、夜レチノール、朝ビタミンCといったように、同時にではなく、異なる時間に分けての使用をおすすめします。
また、優秀な成分で大人気がゆえに、劣悪なレチノールコスメが多数存在するので、この記事を参考に、正しい知識でレチノールコスメを選んで頂き、皆様の肌悩みが解消され、肌がより美しくなることを期待しています!
※本記事の内容は個人の見解であって効果を保証するものではありません